�Q�O�O�O�N�P�P���Q�V���i��Q�E�S���j�����s�j
News Source of Educational Audiology
���\��@
�݂݂����
�@��R���@
��S�O�P��
�@�ʊ��S�W�U��
�ҏW�E���s�l�F�݂݂�����A���� �Ɓ@���V�X�O�|�O�W�R�R�@���Q�����R�s�j�J�T���ڂQ�|�Q�T�@FAX:089-946-5211
�w�Ǘ��Ɖ�E�V�K�w�ǐ\���E�L�����e�Ɖ�Ȃǂ́A�X�ւ��e�`�w�ł��₢���킹�����������A
���L�̃A�h���X�փ��[���������艺�����B
�����@�Ɓ@:h-tachi@ma4.justnet.ne.jp
�u�݂݂����v�z�[���y�[�W
�y�[�p�[���f�B�A�ɂ��u�݂݂����v�w�ǂ̂��U��
�P�P���P�W���@�������搶�����S���Ȃ�ɂȂ�܂���
�搶��1927�N���܂�B1947�N���猚�z�v�̂��d���Ɍg���C1950�N���狞�s�{�V�c�S������w�Z���@��U��o���ɋ����������n�܂�C���S��v�쒆�w�Z���@���o�āC1959�N�ɋ��s�{���W�w�Z���@�ɏA�C����܂����B1968�N�ɘW�w�Z���\�����J�݂����Ɠ����ɒ��\���瑊�k�����S���ɂȂ��܂����B1984�N����͑�㋳���w�Œ��͌����@�̍u�`��S��������u�t�����߂ɂȂ��Ă����܂��B1987�N�ɘW�w�Z�����ސE��́C���Ɉ�ȑ�w�̔��u�t�C�V���q�A�����O�N���j�b�N�̊J�݁E�^�c�C1993�N����͐_�ˑ�����Õ��������w�Z�Łu���o��Q�v�̍u�t�����S���Ȃ����܂����B
�y�ڎ��z��S�O�P��
| NEXT | BACK |�u�݂݂����v�z�[���y�[�W |
|
�����{����I�[�f�B�I���W�[�̊J�c�@�@�������搶����
(����)���
|
|---|
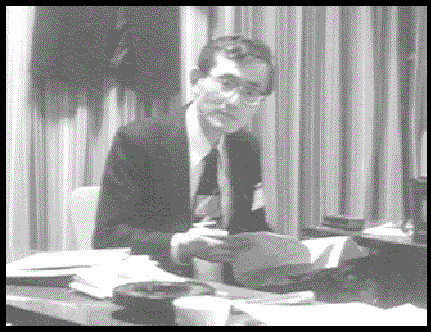
�P�P���P�W�������搶�����S���Ȃ�ɂȂ�ꂽ�B���s�ł̕⒮�����̍ۂɁC�������̕a�@�ɂ��������Ɏf�킳���Ă����������̂����C���̎��͓��a�����Ƃ͌����C�����̂悤�ɔw���s���ƐL���C�u����`�C�����������搶���������ǂ˂��C���ǁC�ނ��킩���ĂȂ��˂��v�Ƃ����悤�Ɍ���������]������Ă���ꂽ���Ƃ��v���o���B�x�b�h���ɏ������b�c�v���[�����u���Ă������悤�ɋL�������邪�C����������ŁC�^���m�C���炢�Ȃ班���͂킩�鎄�ł����߂ĕ����悤�ȃX�s�[�J�ł������ɂȂ肽���̂ł͂Ȃ����낤���Ǝv���Ȃ��璷�����w�Ɍ������ċA�����B
������́C���s�W�w�Z���炲����܂ŁC�_�˘W�w�Z�̓����̒��\��C�����������搶�Ǝ��̎Ԃł����肵�����Ƃ�����B�a�ł����Ԃ�Ƃ�����܂Ŏ��Ԃ��������Ă��܂������C�Ԓ��C�搶�̂�����̃��X�j���O���[���̘b���f���Ă����̂ŁC���͂Ă�����u�܁C������Ɗ���Ă����āE�E�E�v�Ƃ����|��������������̂Ǝv���Ă������C���̍ۂ͊ՐÂȍ���̂�����O����q�����������ɏI����Ă��܂����B�����P�R�N�قǑO�̂��Ƃł͂Ȃ����낤���E�E�E�B
���̕⒮��t�B�b�e�B���O�̎t��������ƌ�����Ȃ�C��P�͌̈���G�搶�ł��낤�B����搶�ɂ͂��̑����Ƃ��w�ŃN���N���b�ƃg���}���Ȃ���C���Ƃ́u�ǂ���������悤�ɂȂ閂�p�v�Ńt�B�b�e�B���O�����Ă����悤�ȋC�����Ă����B���͂���͔��ɑ厖�Ȃ��ƂŁC�u���\������̂͂Ȃ���̂��C����͐l�Ԃ̐S�̖��ł���v�Ƃ̋��������B����C�����Q�Q�̎��́C�����Ɂu�Z�p�v������Ȃ����Ƃ������Ă������C�����@�̑Ό��Ɗ����̒��ŁC���_�̂悤�Ȃ��̂�~�������Ă����B
���̐܂�C���É��Œ��o�����Q������J�Â���C�Q�������܂�C�����搶�̔��\��q�����邱�Ƃ��ł����B�r�o�k�O������p���āC�����ƃC�R���C�Y�ő��p臒l��]�����C�܂��C����臒l�ƒP�ꗹ��x�Ƃ̊W���N���A�Ɏ����ꂽ�����\�ł͂Ȃ��������Ǝv���B���͂��̌�����̋x�ݎ��ԂɁC���[�v�̍��M�̂��Ƃ����₳���Ă����������̂����C���ɃX���X���b�Ɛ}�ʂ������C�u�����ăL�~�˂��C����͂����Ȃ����C�R���͓̂�����O����Ȃ��́B������ɂˁE�E�E�v�ƁC���[�v�ɗ���Ȃ����s�����̒����������Ԃ�ƕ������Ă����������B
���̌�C���x�����s�{���W�w�Z�̒������ɗ�����点�Ă����������ƂɂȂ����B�ǖʂɎq�ǂ��̖��O�ƕ⒮��̊�킪���R�ƌf������C�l�t�@�C�����P���P���Ă��˂��ɒԂ����Ă���l�q��q�������B�a���j�̃^�}�S�Ɍ������C�_�C���������Ĕ����Ȓ��������邨�p��q�������B���̐��R���͓����̓����W�ɂ͂Ȃ����̂ł������B�������̌l�t�@�C�����̂������Ă��������Ȃ���C�u�������������P�[�X�ɂ́C���������Ώ����E�E�E�v�ƂP�P����������ē����ɋA��C���ۂɎ����Ă݂��B�V�[�����X��284PPAGCI�C���Ẳ��҃I�[�e�B�R����E28P�C���C�f�b�N�X��A12T��A18T�i����͎K�т邯�NJm���ɉ����̂����⒮�킾�����j���������B
�������狞�s�W�̒������̋@��ɂ͋����Ă����B�J�Z�b�g�e�[�v���R�[�_�̓i�J�~�`�C�X�s�[�J�͂i�a�k�̃V���O���R�[���E�E�E�C�I�[�f�B�I������Ă���l�Ԃł���ΐ����̋@�����ł���B�u�������v��ڎw���p���C�P���a�C�Q���a�������ɂ������v�Z���C�u�����ʂɂ�����C����Ȃɑ傫���̂ɁC���ꂪ�����ł�����Č����̂��v�Ƃ����悤�Ȏp���Ɏ��͉��ɂ������搶�́C�܂��ɔw���L�т��������������C�傢�Ɋw�����Ă����������B
���s�W�w�Z���ސE��C�V���w����n���S�łP�w�s�����ꏊ�Ƀ}���V�����̈ꎺ������u�V���q�������O�N���j�b�N�v���J�݂��ꂽ�B���s�W�w�Z���ォ��\���L�܂�C�F�{���n�ߋ�B�C���l�����甩���搶�̂��Ƃɕ⒮��̃t�B�b�e�B���O���k�ɖK���e�q���₦���C�ɒO��`�߂��ɏꏊ���m�ۂ��ꂽ�Ǝf�����B�����ɂ����x�����ז������Ă����������B���ւ�����ĉE�艜�ɏ����ȑ䏊������C�①�ɂ��������B���ɂ͂k�g�P�S���u���Ă������B���I���̃E�H�[�u���g�[�����M��ƁC�V�[�����X�̌^�Ԃ͖Y�ꂽ���C�C���s�[�_���X�ƕ⒮��̉����������Ƃ������ȑg�ݍ��킹�̑���킪�������B�ǂɂ͓����C�����{�̕⒮��t�B�b�e�B���O�̑��l�� �n�ӎ��Y�搶�̃N���j�b�N���܂˂��āC�S���̂ǂ����牽�l���Ă��邩���킩��悤�ɁC���{�̒n�}�ɂP�O�l�̐j�C�P�l�̐j�ƐF�����߂��j���h�����Ă����B
�����̂��łɑ��ɍs�����Ƃ��ł���`�����X������ƁC�搶�̃N���j�b�N�������˂��B���̓����F�{����e�q�����Ă����B���k���́E�E�E�m���C�P���ԂR�O�O�O�~�������悤�ȋC������B�ł��C���w���Ă��鎄���������т�Ă��܂��قǁC���̕ی�҂̕��̘b���C���k���Ă����B�⒮��̃t�B�b�e�B���O�͂����Ƃ����ɏI����Ă���̂ł��邪�C���X�Ƌ����i�w�̑��k���Ă���ꂽ�B�����搶�́C�������E�������ł��苳��҂ł������B�a���j�ɗ����������Ȃ���C���̑����̌���������(��)�Ă���ꂽ�̂��B
�R���ԋ߂��ɂȂ������낤���C����ł��u�R�O�O�O�~�v�Ȃ��C�悤�₭�e�q���A��ƁC�①�ɂ���ʃr�[���������Ă����C�u�܂��C���݂܂��傤��v�Ƃ��̂܂ܐ��{�̃r�[���������낤���B������v���C���̎����炢���炲�̒����悭�Ȃ������̂��C�u���̍��˂��E�E�E�v�Ɖ��x�����f������x�Ɋʃr�[���̖{��������C�߂��̂�������[���ł̂��H���������Ă����悤�ȋC������B
���p�����肨�ʖ�ɂ������V�ɂ��Q�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
�ł������炭�C�����̊W�҂Ɉ͂܂ꂽ�����ł��������낤�B
�����搶�́C�����{�̒��\�̐��ł���C���C���C�ȋߋE����I�[�f�B�I���W�[�̊J�c�̈�l�ł�����B�搶�̓p�[�t�F�N�g��ڎw���搶�ł������B�������̌��e��e�L�X�g�����߂Ă��Ȃ���C���Ȃɐ��Ȃ��d�˂��邽�߂ɁC���ɏo�����͔̂��ɏ��Ȃ��B���̌������ƙ{���ʂ��́C�������Ƃ��Ă̐搶�̐��i�䂦�ł��낤�B����䂦�Ɏf���Ƃ���C����N�܂Łu���o��Q������ɂ����鉹�������̊�b�v����e�L�X�g��Z�߂��Ă������o�łɂ͎����Ă��Ȃ��ƕ������B
�����搶���S���Ȃ����B�搶�ɂ��܂Ƃ߂��������������Ƃ͂���Ȃɂ���B�܂��܂��茳�ɃS���S�����Ă���B�ł��C�S���Ȃ��Ă��܂�ꂽ�B�{���ɖ{���Ɏ��c���ꂽ�Ƃ����悤�ȋC�����ɂ����Ȃ�B���n�ɂāC�����V�̎��Ԃ��}���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��������C�u�����搶�̈̋Ƃ��㐢�Ɉ��p���C����I�[�f�B�I���W�[�̗���������ɂ���ɐ}��g������X�͑����ꂽ�̂��v�Ɗ����C�勃�����Ă��܂����B
�u�搶�C���肪�Ƃ��������܂����B�킩��Ȃ����ƈ�t�����ǁC���C�Ȃ�Ƃ�����Ă܂��B�v
�y�ڎ��z
�V���}���Љ�
|
�@�哈 �����@�\���͋�̋ɂ݂܂� |
|---|
�P�X�R�P�N��苳���Ƃ��ĂP�X�T�P�N����͂P�X�X�T�N�̒����ɓn���āA���{�W�b�w�Z���߂�ꂽ�哈���搶���S���Ȃ����̂͂P�X�X�W�N�U���P�X���̂��Ƃ��B�哈�搶�͐�O�̘W����C���̘W�w�Z�`�����C�I�[�f�B�I���W�[�C��������̐��҂ł���C�܂��ɓ��{�̘W�����ł����Ă���P�l�҂ł��B �����āC�u���E�̃C�T�I�v�ƌĂ��قǂɁC���E�̒��o��Q������̐��i�C���ł��A�W�A�̘W����̐��i�ɂ͑傫�Ȏd�����Ȃ���Ă���ꂽ�B
�{���͑哈�搶���S�T�N����X�T�N�ɂ����ĂT�O�N�ɓn���ď����ꂽ����������ʂɂ܂Ƃ߂����̂ł���B�P�X�V�P�N�ɂ͓�w���Ƃ������O���̂��Œ萧�̃C���[�W������C�ʋ������s����ׂ��ł��邩��u���o�����v�Ƃ����悤�ɕς��������ǂ��Ȃǂ̎w�E������Ă�����C�����ŊJ�Â��ꂽ���E�W�����c�Ɍ����đ�ςȏ�����ςݏd�˂�ꂽ���ƂȂǂ��ǂ݂Ƃ��B�P�X�W�T�N�ɂ́C��b�ɂ��Ă������ɂ��āC�哈�搶�����͂𒆗�����ƌ������Ă��܂������ł��킢���C�u��b���������Ƃ������Ƃ�W�w�Z���S�O���ׂ����R�͏������Ȃ��v�Ə����Ă�����B
�u���U�����v�Ƃ������ʐ^���ڂ��Ă���B�U�T�N�Ԃɓn���ĘW����Ɍg��邱�Ƃ͎���̋Ƃł���B�����̘W�w�Z�ł��ٓ����Ȃ��Ƃ����O��ōŒ��ł��R�W�N�قǂ����x�C�哈�搶�̖��܂ł�����E�ł��Ȃ��B�U�T�N�Ԃ̒����ɓn��C�Ђ�����ɘW�����簐i����Ă���ꂽ�搶���C���̎���C����̔w�i�̒��ŁC�ǂ̂悤�Ȃ��l����������C���ꂪ�ǂ̂悤�ɕω����Ă������C���̌o�܂̗��j�ɂ��Њw�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ɗ������B

�P���Q�O�O�O�~�i�����S�O�O�~�j�B
����͉��L�̕��@�ɂ�
- �P�F��������
-
�P�����Q�S�O�O�~�����L�ɑ����B
��195-0063 ���c�s��Óc��1942
���{�W�b�w�Z������
TEL:042-735-2361
- �Q�F�X�U��
-
�O�O�P�R�O�|�V�|�T�Q�P�Q�P
�������`�F���{�W�b�w�Z
���l���Ɂu�{��v�ƋL�����C�P�����Q�S�O�O�~×�����𑗋�����B
�y�ڎ��z
�r�f�I�Љ�
|
�@�@�� �� �� �Y �� �� �� �� �� |
|---|
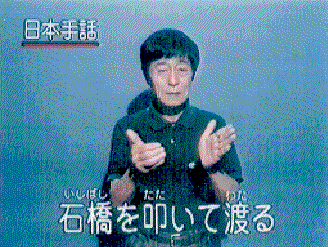
�u���̃r�f�I�́E�E�E�v�i������̈ē����j
�{�҂́A����悭�g���邱�Ƃ̑�����\�I�ȁu���Ƃ킴�v�V�O���I�сA���^���Ă��܂��B
�܂����{��b�Łu���Ƃ킴�v���̂������A���ɂ��́u���Ƃ킴�v�̈Ӗ���p�����{��b�ʼn�����Ă��܂��B�܂��A�t�^�̉�����ɂ́A���^�����u���Ƃ킴�v�Ƃ��̉���̓��{����Ă��܂��B�悸�A�����Ŏ�b���l���Ă��������A���̌�r�f�I�����āA�m�F������A�ӏ܂�����A�͕킵���肷����@������܂��B
�Â�����`�����A�����̐l�X�Ɏg���Ă�����������́u���Ƃ킴�v�̒�����ɓ����Y�搶���I�����A����ɐ搶�̓Ƒn�����������Ă킩��Ղ����������ꂽ�\���ɂ��Ă��܂��B
�w�Z��c�́A�T�[�N���̊F�l�̊ԂŁA���̃r�f�I�����������Ɏ�b�\���̗ւ��L���āA�V���Ȉӌ��₲��Ă������ǂɂ����������B
������ɂ���悤�ɓ��{��b�����Ă���Ɓu���`�Ȃ�قǁA����ȕ\�����I�v�ƁA���̕\���̖L������Ӗ���`����\���̔��z�Ɋ������Ă��܂��B�g�[�^���R�~���j�P�|�V�����������B
�P�{ �R,�T�O�O�~�i�������݁F�T�{�ȏ�ꊇ�ő�����������j
�������@�F���L���e�`�w����B����̓r�f�I������A�P�O���ȓ��ɓ����̐U���p���ŐU�荞�ށB�Ɖ��F�s�b���E�ʖ� �[�ԗl���i��253-0012 ������s���a�c 3-8-35)
�@�r�f�I�u�ɓ����Y�̂��Ƃ킴�v�\�����@�@���M��e�`�w�F�O�S�U�V�|�T�Q�|�P�S�S�Q
�@�ӂ肪��
�@�����O�F�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�@�@�@��]�����i�Q�Q�Q�Q�Q�j�{
�@�A����F�i�X�֔ԍ� �������|�������� �j
�@�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q
�@�A����F�d�b�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�@�e�`�w�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q
|
�y�ڎ��z
�V���}���Љ�
|
�@�@�� �� �� �G �� �� �� |
|---|
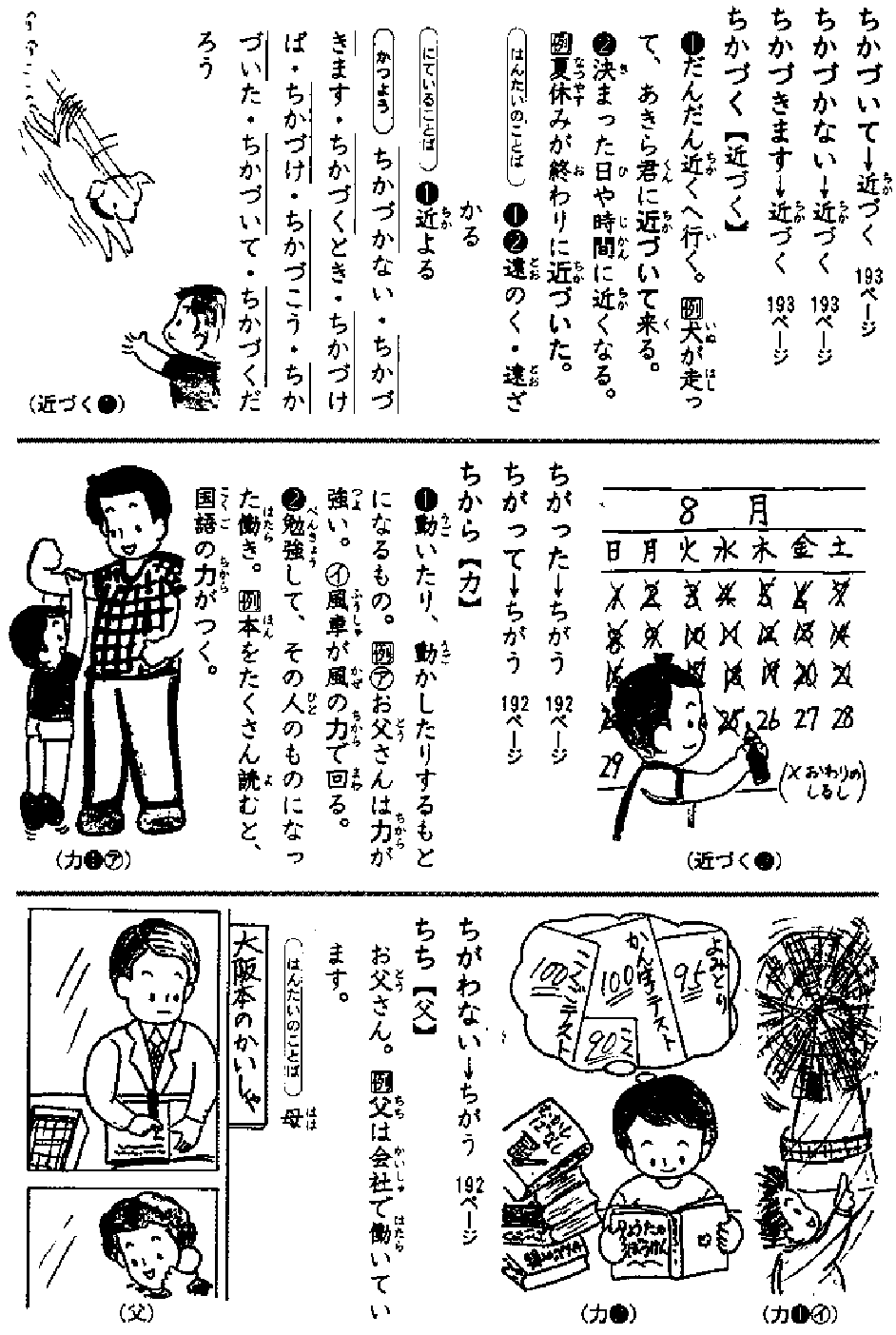
�������E�̍ۂ͂��Ԃ�p�쏑�X����o�ł���Ă����u���ƂΊG���Ă�v�𗘗p���Ă����悤�ȋL��������B������Ƃ������Ƃ�`���������ɓK�ȊG�Ǝg�p�@���q�ǂ����g�����ׂ��鎫�T�͂Ȃ��Ȃ��Ȃ��B
���́u�������G���Ă�v�́C���������Y�݂̌��ʂȂ̂��낤���C�����s���W�w�Z�̐搶�R�l�����N�̘W�w�Z�ł̋�����H�����ƂɕҏW�ɂ����������Ă�ł���B���ꂾ���Ɋ��p�`�Œ��ׂ�ꂽ��C�C���X�g��ᕶ�ɂ킩��₷�����̂��I��Ă���B�����ɂ��W�w�Z�I�ȏ�ʐݒ�Ɋ�Â��ᕶ�������C�ǂ݂Ȃ���u��������������ʂ��������Ȃ��v�ƃj���j�����Ă��܂����B
�C���X�g���L�x�Ȃ̂ŁC�C���X�g�����Ȃ���G�{�̂悤�Ɍ��Ă������Ƃ��ł��C�c�t���S���炢���珬�w���܂Ŏg���邩�Ȃ��Ǝv���B
�P�� �Q�O�O�O�~�i�ŁE�������݁j
�Ȃ��C�ʏ�̏��X�ł͍w���ł��Ȃ��̂ŁC���L�̕��@�ł��������B
- �������@�F
-
���L�̒��������e�`�w����B�e�`�w���Ȃ��ꍇ�͉��L�ɒ����[��X������B
��661-0035 ���s���ɔV��2-13-17 �������G���Ăs��
�@�������G�������@�@�@�@�@�@���M��e�`�w�F�O�U�|�U�S�R�U�|�Q�P�T�V
�@�ӂ肪��
�@�����O�F�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�@�@�@��]�����i�Q�Q�Q�Q�Q�j��
�@�A����F�i�X�֔ԍ� �������|�������� �j
�@�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q
�@�@�@�@�@�d�b�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�@�e�`�w�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q
|
�y�ڎ��z
�V���}���Љ�
|
�@�@������̖{�u�n�[�g�͂Ȃɂ���v |
|---|

�{���͘W�w�Z���@�C��w���S�C������Ă���ꂽ�c�����q�搶�̎���o�ŁB���ꂾ���ɁC���o��Q�����f�f���C�W�w�Z���ł̋���⏬�w�Z�����ɂ��āC��������ʂ���ł��낤��ʂ�ʂ��ė��������i�����悤�ȍ\���Ɠ��e�ɂȂ��Ă���B
���E��
�u�n�[�g�͂Ȃɂ���v�́A��t�s���@�����w�Z��w����S�����Ă���������c�����q�搶���A�P�N�Ԃ̌��C�̋@��ɒ��J�ɍ��グ��ꂽ������̂��߂̈���ӂ��G�{�ł��B���o�ɏ�Q�������w�����w�Z�����ŏo��l�X�ȋ�̓I�Ȗ�肪�A�q�ǂ������̎��̌�����W�߂��Ă��܂��B����Ɖ߂����Ă����c���搶�̂���܂ł̌o�����A�G�{�̌`�Ō����������̂ƌ�����ł��傤�B���Ƃ��킢���f���炵���G�ŁA���w�Z��w�N�̎q�ǂ������ɂ��������̏�Q�������炷�������R�ɓ`���邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B�����̕��̃n�[�g��g��������G�{�Ƃ��Đ��E�������܂��B
�}�g��w�S�g��Q�w�n�����@�֓����a�@
�P�� �Q�O�O�O�~�i�����ʁj
�Ȃ��C�ʏ�̏��X�ł͍w���ł��Ȃ��̂ŁC���L�̕��@�ł��������B
- �������@�F
-
���L�̒��������e�`�w����B�e�`�w���Ȃ��ꍇ�͉��L�ɒ����[��X������B
��266-0014�@��t�s������948-97�@�c�����q�搶
�@�u�n�[�g�͂Ȃɂ���v�������@�@�@�@�@�@���M��e�`�w�F�O�S�R�|�Q�X�P�|�T�W�R�T
�@�ӂ肪��
�@�����O�F�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�@�@�@��]�����i�Q�Q�Q�Q�Q�j��
�@�A����F�i�X�֔ԍ� �������|�������� �j
�@�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q
�@�@�@�@�@�d�b�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�@�e�`�w�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q
|
�y�ڎ��z
�V�����q�Љ�
|
�@�@�w�K�w���̍H�v�Ƒ����I�Ȋw�� |
|---|

���w���厖�̗щ��}�搶�́C�{���́u�͂��߂Ɂv�Ŗ{���̕K�v����W�X�Ɛ����Ă���B�u��X���o��Q���̋���Ɍg���҂́C���k��l�ЂƂ�̎��Ă�͂��ő���L���Ă���ƌ������̂ł��낤���H�v
�P�Q�O�N���钷�����o��Q������̗��j�̒��ŁC��b�@�Ɏn�܂�C���b�@�C�⒮�C�ēx�C��b���܂ރR�~���j�P�|�V�������[�h�̐��������}���C���͐����Ă����B�������C�u����w�ю���l����́v���\�ɐg�ɂ��邱�ƂɎ������ł��낤���B���̂�����ɒ��o��Q������̑傫�ȉۑ肪���邩�Ǝv���B
���āC�{���͒}�g��w�����W�w�Z���w���̎��H�E�������ł���B���̒��ɂ͓��X�C�����I�w�K�Ɍ��������H���Ïk����Ă���B�ēx�C�ю厖�̕������p����B
�������C����ł��C�܂��܂��q�ǂ������̗͖͂����Ă���B��X���t�������o���Ă��Ȃ���̎R��������Ă���悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B�q�ǂ������̗͂��ő�������o���Ă��C�����܂����Љ�Ŋ���ł���l�ނɈ�ďグ�邽�߂ɂ͉����K�v�Ȃ̂��H�@�{�Z���Z���E�n�ꌰ�́i�����j�C�W�w�Z�̋����Ƃ��ĕK�v�Ȃ��̂́C�u�����点��Z�p�v�ł���ƁC�����ɒf�����Ă���B��������X�́C���B���������̗�����t���Ɋ��p���C��z������含�ɂ���āC���o��Q���̗͂�L���Ă����˂Ȃ�Ȃ��B
�P�� �P�T�O�O�~�i�����ʁj�B�ʏ�̏��X�ł͍w���s�Ȃ̂ŁC���L�̕��@�ł��������B
- �������@�F
- �@���L�̒��������e�`�w����B�A�܂�Ԃ��C�U���p���������Ă���̂ł���ɂč��q��{�����𑗋�����B�B���q���茳�ɒ���
�@�u�w�K�w���̍H�v�Ƒ����I�Ȋw�сv�������@�@�@���M��e�`�w�F�O�S�V�|�R�V�R�|�W�V�V�R
�@�ӂ肪��
�@�����O�F�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�@�@�@��]�����i�Q�Q�Q�Q�Q�j��
�@�A����F�i�X�֔ԍ� �������|�������� �j
�@�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q
�@�@�@�@�@�d�b�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�@�e�`�w�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q
|
�y�ڎ��z
������J��
|
�@�@�����s�낤���猤����E���\���猤���� |
|---|
��ÁF�����s���낤�w�Z�E���\���猤����@
��F�����s���i��낤�w�Z���@�H�J�`��@
|
|---|
�P�D���@���F�@�����P�R�N�@�P���Q�O���i�y�j�@�ߌ�P���R�O���`�ߌ�S���S�T��
�Q�D��@��F�@�����s�������낤�w�Z�i�b���P�K�z�[���j
�R�D���@�e�@�@��@���F�w�e�Z�̋���I�[�f�B�I���W�[�̎��g�݂Ɖۑ�x
�@�@�@�@�@�@�@�ҁF�@������T�@�i���{�낤�j�@�@�O�Y���v�i���˂낤�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���삫����i�����낤�j�@�@�����i�i�k��J���j
�@�@�@�@�@�@�@�u�@���F�w���l������q�������ւ̒��o�x���݂̍���x
�@�@�@�@�@�@�@�u�@�t�F�@����@���I���i�}�g�Z�p�Z����w�����j
�@�@ 13:30�@�@��t
�@�@�@�@�@�@�@�m�⒮��W���n�iصݥ�ů��Eܲ�ޯ������ݥ����� �j
�@�@ 14:20�@�@�J��
�@�@ 14:25�@�@�i�e�Z�̋���I�[�f�B�I���W�[�̎��g�݂Ɖۑ�j
�@�@ 15:15�@ �i�x�e�j�m�⒮��W���n
�@�@ 15:30�@�@�u���w���l������q�ǂ������ւ̒��o�x���݂̍���x
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �m������I���i�}�g�Z�p�Z����w�����j�n
�@�@ 16:30�@�@���^����
�@�@ 16:45�@�@��
�T�D������@�@�R�O�O�~
�U�D��@���@�@�T�O��
�V�D�Q���Ώہ@�낤�w�Z�E��w���̋����y�ђ��o��Q����Ɍg���{�ݐE����
�W�D�\�����@�@�����@�֖��E�Z���E�����E�A��������L���̏�A
�@�@�@�@�@�@�@�P���P�T���i���j�܂łɁA���L���ɂe�`�w�ɂĂ��\�����݉������B
�X�D�Ɖ��@�@�����s���낤�w�Z���\���猤����@��\�@�ԍ��R�@�ˍs
�@�@�@�@�@�@�@�����s���i��낤�w�Z�@�e�`�w�F�O�R�|�R�S�V�S�|�R�P�W�Q
|
�����s���낤�w�Z�E���\���猤���� �Q���\����
�\����\�ҁF�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q
�w�Z�i�����@�ցj���F�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q
������Z�����F�i ���������|���������@�j�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q
�@�@�@�@�@�@�@�d�b�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�@�e�`�w�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q
|
�y�ڎ��z
- �����������Z�@�@�����P�R�N��
- ���������@�K������ďC�@�����@�K�o�Ł@5500�~�@4-8058-4311-X
- �����͕������Ȃ��Ă�
- Jacqueline Keaster���@�R���i��@���|�Ё@1000�~�@4-8355-1018-6
- ���Q�P���I���@��A�ȗ̈�̗Տ��@CLIENT21�i�S�j�O���E����
- �쑺���瑍�ҏW�@���R���X�@31000�~�@4-521-59101-9
- ���Q�P���I���@��A�ȗ̈�̗Տ��@CLIENT21�i�P�P�j���꒮�o���n�r���e�[�V����
- �쑺���瑍�ҏW�@���R���X�@31000�~�@4-521-59091-8
- ���̂Č��݂���ƃ|�`�F���������̂�����
- �L�n���ƒ��@�o�ŎЁ@1500�~�@4-333-01914-1
- ���V�}�����@��A�ȁE���O�ȍu���@�S�F���o�E�����E�A���E�C�ǁE�H��
- �X�R�����ҏW�ψ��@���W�J���r���[�Ё@18000�~�@4-89553-851-6
- ���w�����E�P���[�F��Q�ҕ����̕�
- ����n���@�u�k�Ё@660�~�@4-06-271802-2
- ���̂ł��ڂ����b�\���O�u�b�N�F�Ƃ������ɂȂ邽�߂�
- �V��Ƃ��Ђ����@��؏o�Ł@1800�~�@4-7902-7161-7
- ����b�ł��������{�̓��w�E���̃x�X�g�A���o��
- ���y���ތ�����ҁ@���O�Ё@2500�~�@4-8383-0828-0
- �����ׂĂ̎q�ǂ��ɖL���Ȉ炿���F��Q���ۈ�R�O�b
- ���p���q���@��������o�Ł@1000�~�@4-87699-562-1
- �����R�m��͏�Q������ɂǂ����g��
- ���R�m�꒘�@�����}���o�Ł@1860�~�@4-18-037314-9
- ����Q�����ւ̏���
- �L���@�O�ďC�@���{�����Ȋw�Ё@2500�~�@4-8210-7312-9
- ����Q�w�����
- �q�{�q���Ғ��@���䏑�[�@2000�~�@4-88720-304-7
- ����Q�ƃ��n�r���e�[�V�����厖�T
- �f���E�I���g�ҁ@����P�B�Ė�@�Ó�o�ŎЁ@38000�~�@4-88209-021-X
- �����O��E���W�Â̎��
- ���a��w���O��E���W���f�ÔǕҏW�@�����o�Ł@2000�~�@4-307-25712-X
- �����������̂���܂��F�����P�Q�N��
- �呠�Ȉ���ǕҏW�@�呠�Ȉ���ǁ@320�~�@4-17-352531-1
- ����Q�҉^���ƕ����F���۔�r�ɂ���Q�҃G���p���[�����g
- �ڍ��P�����@�P���Ё@2800�~�@4-7699-0930-6
- �����{�ꉹ�C�����j�̌���
- ���c��t�F���@�g��O���ف@11000�~�@4-642-08521-1
- �����������̎w���F�V������Q������ւ̎��g��
- ����M���ҁ@����o�Ł@2600�~�@4-316-33880-3
- ����Q���̂��߂̎��ƂÂ���̋Z�@�F�ʂ̎w���v�悩����ƌ����܂�
- ���c���ȕҒ��@�t�����[�@2300�~�@4-654-00055-0
- �������
- �ΐ�T���Ғ��@����Ё@2400�~�@4-7679-4504-6
- ����Q���̐e���猒�펙�̐e�ցF�����ۈ炪������O�̐��̒��ɂȂ邱�Ƃ������
- �Έ䗘���ҁ@��돑�[�@1400�~�@4-88602-620-6
- ���d�ǐS�g��Q�ʉ��}�j���A���F�ݑ�����x���邽�߂�
- �]�����F�ďC�@�㎕��o�Ł@2600�~�@4-263-23248-8
- ���m�I��Q�ҒD��ꂽ�l���F�s�ҁE���ʂ̎����ƕٌ�
- �����m�����@���Ώ��X�@2000�~�@4-7503-1343-2
- �����B��Q�����Q�O�O�P
- ���{�m�I��Q�����A���ҁ@���{�����Ȋw�Ё@4000�~�@4-8210-7307-2
- ���v���F���B�E�w�K�E����Տ��̐S���w
- ���c�ƕF�Ғ��@�k��H���[�@2500�~�@4-7628-2199-3
- ���e�|���c���S���Ö@�F�ꐫ�̃R���X�e���[�V����
- D.N.�X�^�[�����@���w�p�o�ŎЁ@5000�~�@4-7533-0011-0
- ���Ԉ֎q�E�Ж�Ⴢ̐l�ł��ł��郌�N���G�[�V�����Q�[���W
- ����O�Y���@�t�����[ 1300�~�@4-654-05755-2
- �����ǂƔ��B��Q�����̐i���S
- ���ؗ��Y�ҁ@���a���X�@5800�~�@4-7911-0411-0
- �����o�S���w�ւ̏��ҁF�����̐��E�ւ̃A�v���[�`
- ��R�����@�T�C�G���X�Ё@2200�~�@4-7819-0963-9
- �������̕����̓����Q�O�O�O�N
- �������v����ҏW�@�������v����@1800�~�@�w�����̎w�W�x�Վ����� ��47����12��
- �����ǂƐS�̔��B�F�u�S�̗��_�v���z����
- R.�s�[�^�[ �z�u�\�����@�w���Ё@5200�~�@4-7614-0005-6
- �����q���j�̕����v���F��Q�ҁu�����P���~�v����̒E�o
- ����F�ے��@���w�ف@533�~�@4-09-405101-5
- ��������Ƒ��ɂȂ����Ƃ�
- �Γc�r�_���@WAVE�o�Ł@1500�~�@4-87290-091-X
- ���n�j�[���ӓ����ɂȂ�܂�
- �L�������C���E�A�[�m���h���@���y�Ё@1400�~�@4-337-06239-4
- ���Y�o���A�u���傤�����v����F�킪�l���ɉ����͂Ȃ�
- �X�C���@����o�ŎЁ@1200�~�@4-7592-6110-9
- ����a�̎q�ǂ���m��{�T�F
- ��q�@�匎���X�@1800�~�@4-272-40395-8
|
�y�ڎ��z
- ������ƈ�w�@48(12)2-3,2000
- �u�V�̐�͐S�̃o���A�H�v�����q
- �����@��A�ȁE���O�ȁ@72(12),2000
- �u�⒮����I�x���̎d�g�݂ƌ���v�����A�V�@796-802
- �u�⒮����X�̔F��v�{�i�D�́@803-806
- �u�⒮��̊��I���v�����ꋻ�@807-810
- �@�u���n��Ƃ̂��߂̕⒮��̃t�B�b�e�B���O�v����F���@813-816
- �u�⒮����ʂ̕]�����@�v���{�q�l�@818-824
- �u�l�H�����̓K���ƌ��E�v�ɓ����@827-831
- ��The Volta Review�@101(1) 5-29,1999
- �uMultichannel Cochlear Implantation and the Organization of Early Speech�v
- �@H.A.McCaffrey,B.L.Davis,P.F.MacNeilage,D.Hapsburg
- ��DEAFNESS&EDUCATION INTERNATIONAL�@2(3)142-151,2000
- �uUsing Listening Progress Profile to assess early functional auditory
- �@performance in young implanted children�v
- �@T.Nikolopoulos,P.Wells,S.M.Archbold
- ��Language Speech and Hearing Services in Schools�@31(4),2000
- �uThe Benefits of Sound Field Amplification Classrooms�v
- �@A.E.Brophy,H.Ayukawa�@324-335
- �uImproving Acoustics in American Schools�v
- �@P.B.Nelson�@354-355,389-390
- �uAcoustical Barriers to Learning:Children at Risk in Every Classroom�v
- �@P.B.Nelson and Sig Soli�@356-361
- �uClassroom Acoustics for Children With Normal Hearing and With Hearing Impairment�v
- �@C. C. Crandell,J. J. Smaldino�@362-370
- �uClassroom Amplification Technology: Theory and Practice�v
- �@J.J. Smaldino,C.C.Crandll�@371-375
- �uTen Ways To Provide a High-Quality Acoustial Environment in Schools�v
- �@G.W.Siebein, M.A.Gold, G.W.Siebein,M.G.Ermann�@376-384
- �uThe Classroom Acoustical Environment and the Americans With Disabilities Act�v
- �@D.L.Sorkin�@385-388
- Appendix�uImproving Acoustics in Classroom Acoustics Working Group�v391-393
|
�y�ڎ��z
�@��Љ�
|
�@SONY
�@�q�l�|�o�r�V�s�u
|
�@�X�s�[�J�t�������[�g�R�}���_ |
|---|

���̑��u�́u�ԊO����M��ƃA���v����������e���r�̃����R���v�Ƃ������\���ɂȂ��Ă���B�e���r�ɐڑ������ԊO�������킩��C�ԊO���ɏ���ăe���r�̉������o�āC�茳�ɂ����M��ɓ͂��B��M�푤�ɂ̓A���v����������Ă��āC�e���r�̉�����������ăX�s�[�J����C�܂��͐ڑ������C���z���Ȃǂ��特�Ƃ��ďo�͂����悤�ɂȂ��Ă���B���C�e�탁�[�J�[�̃e���r�ɂ��킹���郊���R���@�\�������Ă���B
���̑��u�̎�M��ɂ͂R�̓��͕��@���p�ӂ���Ă���B���͍��܂Ŏs�̂���Ă������l�̋@��ł́C���̃e���r�̉�������镔�������܂��ł��Ă��Ȃ����߂ɉ����e���r������o���Ȃ����Ƃɖ�肪�������B�{��͎莝���̃e���r�ɂ���ē��͕��@���I���ł��C���̕ӂ̑���ɂ̓u�����h�Ȃ�ł͂Ɗ��S�����B
�ԊO�����g�p���邽�߉������ɂ߂ėǂ��B��M�푤�̓����X�s�[�J���܂��܂��B����ɖ{��̊J���҂͓�҂Ƃ������Ƃ������āC�C���z���W���b�N�𗘗p���ăV���G�b�g�C���_�N�^��O�����͒[�q�Ȃǂ���ĕ⒮��Ńe���r�̉������Ƃ��ł���B
��r�I�y����ł���Ζ{�킾���ŏ\���Ƀe���r�̉������Ƃ��ł��悤�B�܂��C�����g���q�ǂ����������r���O�̒��ŏd�Ă���̂����C�u���p�i�v�Ƃ��Ă��\�ɒʗp����B
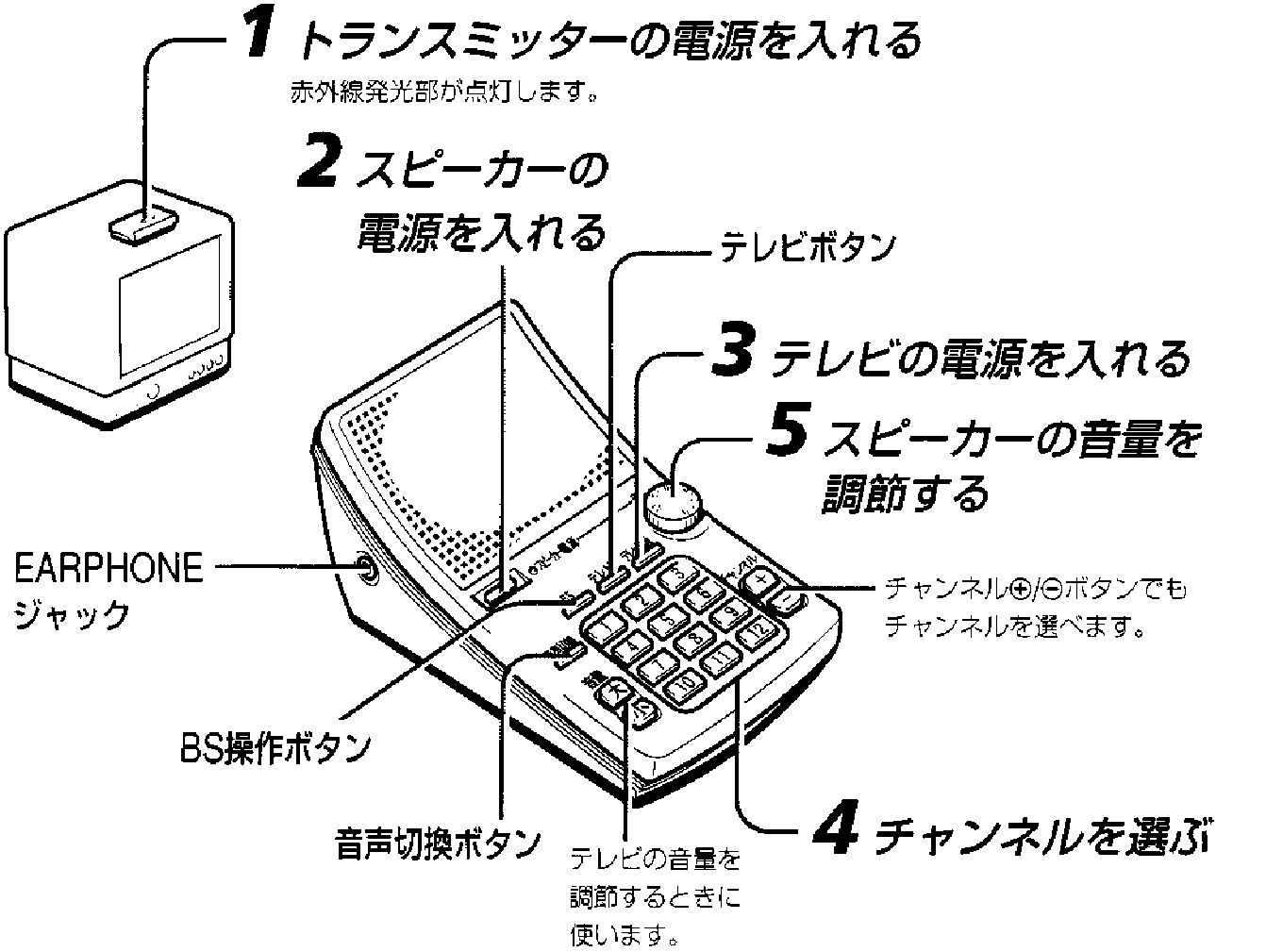
�Ȃ��C�ŋ߁C��M��ɂ`�b�A�_�v�^�ɂ��d���������ł��� �q�l�|�o�r�P�O�s�u�����C���i�b�v�ɉ�������B�V���i�ɂ͔��M�E��M�̑o���Ƃ��ĂQ��̂`�b�A�_�v�^�����Ă���ق��C�������傫���Ȃ�C���₷���Ȃ��Ă���B
���i
�@RM-PS7TV 8800�~
�@RM-PS10TV 10800�~
�y�ڎ��z
������J��
|
�@�b�a�q�L���p�V�e�B�r���f�B���O �Z�~�i�[
|
|---|
�J���r�㍑�́C�Ƃ��ɒn���ɂ������Q����̃v���O������T�[�r�X�W�����邤���ŁC�b�a�q���ʂ����Ă��������������]������Ă������C�b�a�q�����𐄐i�C�x������l�ނ��܂��܂��s�����Ă��邽�߁C���������ۂɓW�J����Ă���n��́C����߂Č����Ă���̂�����ł��B���������āC�b�a�q�������i�\�Ȑl�ވ琬�́C�}���Ǝv���Ă��܂��B����̌��C��ł́C���n�̃��[�J�[���ǂ̂悤�Ɉ琬�C�x�����Ă����邩���Ƃ��ɍl�������ƂƂ��ɁC�����O�o���ɂb�a�q�̗�����[�߂�@��Ƃ��邱�Ƃ��Ӑ}���Ă��܂��B�J���r�㍑�̕�������̔��W�͉v�X�C�n��i���ݔ_���C�����ɂ����Ă͂b�a�q�����𐄐i�C�x������l�ނ��s�݂̂��ߒ蒅���Ă��܂���B
�b�a�q���Ɛ��i�\�Ȑl�ވ琬���}���ƍl���C���n���[�J�[���ǂ̂悤�Ɉ琬�C�x�����Ă����邩�����O�o���ɂb�a�q�̗�����[�߂�@��Ƃ��܂��B�Z�~�i�[�ł͂b�a�q�������o�������l�������҂Ƃ����O���[�v�ʂ̃��[�N�V���b�v�`���Ŏ����ʂ����f�B�X�J�b�V�������s���܂��B
�P�D���@���@�@�Q�O�O�P�N�P���Q�W���i���j���j�@�ߌ�P�O���`�ߌ�S��
�Q�D��@��@�@�����s�a�J���ʃ��J�R�|�W�|�T
�@�@�@�@�@�@�@���{���w�Ö@�m��فiTEL:03-5414-7911�jJR���h�w���k���V��
�R�D�Q����@�@��l�@3,000�~�i���H��@��������܂ށj
�@�@�@�@�@�@�@����O�@5,000�~�@�\�����ݏ��@�S�O���܂�
�S�D���@�e�@�@�b�a�q�����̂��߂Ɂ@�@���{�b�a�q�l�b�g���[�N�@�n�Ӊ�s
�@�@�@�@�@�@�@�O���[�v�ʃ��[�N�V���b�v�@�@�S�O���[�v���x�ɕ������
�@�@�@�@�@�@�@�S�̓��c�E�܂Ƃ�
�T�D�Ɖ��@�@JANNET�����Ǔ��{���n�r���e�[�V����������@���x�q�^����D�q
�@�@�@�@�@�@�@TEL:03-5273-0601�@FAX:03-5273-1523�@e-mail:hirano@dinf.ne.jp
|
�y�ڎ��z
�~�j�j���[�X
|
�@�F���s�Ŏ����t���f���f
|
|---|
�R�����F���s�̉f�掩���f�c�́A�F���V�l�}�N���u�́A�P�Q���P�U���ߌ�U������A�F���s������قʼnf��u�n����T���E�i���v�i�\�����ēj�̎����t����f�o��Q�҂�Ώۂɍs�����B���̉f��̓Z���t�ɉp��Ɠ��{��Ƃ��������邪�A�p��̃Z���t�ɂ͓��{�ꎚ�����ŏ�������Ă���̂ŁA���{��̃Z���t�ɂ��āA�\���ē̗����̌��A�v��M�L�T�[�N���F���i���c���]��j�������t�����s�����B��f��A�\���ē̍u���������ōs���A����ɂ��A�n�g�o�v��M�L�E��b�ʖt����ꂽ�B
�y�ڎ��z
�q������
|
�@�� �{ �� �� �� �� �� �f �� �� ��
|
|---|
�P���@ �g�n�t�r�d�@�n�E�X�@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�@�@�V���i���j�`�l�V������
�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�P���i���j�o�l�P������
�@�@�@ �ނ�o�J�����C���u���@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�@�P�S���i���j�`�l�V������
�@�@�@ ���E�j�͂炢��@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�@�Q�P���i���j�`�l�V������
�@�@�@ �j�͂炢��@�t�[�e���̓Ё@�E�E�E�E�E�E�@�Q�W���i���j�`�l�V������
�Q���@ �]�Z���@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�@�@�S���i���j�`�l�V������
�@�@�@ ���̉̂��������� �E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�@�P�P���i���j�`�l�V������
�@�@�@ �n�i�̂��]�˂̒ނ�o�J�����@�E�E�E�E�E�E�@�P�W���i���j�`�l�V������
�@�@�@ �{�N�́C��������@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�@�Q�T���i���j�`�l�V������
|
������������ւ̂��ӌ��^���N�G�X�g���� �q������Ґ����܂� FAX:03-5250-2324
��M�Ɋւ���Ɖ�́A�p�[�t�F�N�s�u�@FAX:03-5802-8438���A��L�q������܂ŁB
�ڂ����́A��104-0045 ������z�n4-1-1 �����r���T�e�@�q������܂ŁB
�y�ڎ��z
�����t���f��
|
�@�u �� �� �� �� �� �� �� �� �v
|
|---|
�f��u���̉̂����������v�͎��݂��钮�o��Q�҂̕v�w�A�����v�Ȃ����f���ɕ`������i�ł��B�����v�Ȃ̂��Ƃ́A�s�a�r�̔ԑg��ʂ��āA���邢�͖{��ʂ��Ă������̕����������Ǝv���܂��B�e�n�̘W�w�Z�⒮�o��Q�֘A�s���ɍu�t�Ƃ��ČĂ�Ă��܂�����A���b�ځA�����ꂽ�������邩�Ǝv���܂��B
���炷��
���b�N�����[���ƃW�F�[���X�E�f�B�[���ɓ���A�w������͕s�ǂ��C���A�f�B�X�R�ŗx��܂���d����ȏ��G�i�V�{�ǁj�̎p�́A�͂��ڂɂ͈�ʂ̎�҂ƕς��Ȃ��f��B���A������A�ނɂ͑傫�ȁu���v���������B�R�̎��A���ׂ������点���M���o���A�ނ̎��́u���v�������Ă��܂����̂������B���ʂ�ʂ��ď��G�ƒm�荇�����ޔ��q�i���]�L���j�́A�f�U�C���w�Z�ɐi�݁A�A�E���邪�A���܂��܂ȍ���ɂԂ��肭���������ɂȂ�B����ȂƂ��ޏ���E�C�Â���̂́A���G����̔ޏ��̐S�ɂ�����������u���t�v�������B�ӂ���͂₪�Č������A���Ƀg���C�A�X�����E���[�X�w�̒�����n�߂�B����҂ł����߂炤�悤�ȉ��ȃ��[�X�Ɋ����Ē��킵�A�����Ă����т�S�g�Ō��킵�Ȃ���|�W�e�B�u�ɐl���𑖂葱�����l�̎p�́A�m�炸�m�炸�̂����Ɏ���̐l�X���E�C�Â��Ă�������B
�y�ڎ��z
�E�E�E�ЂƂ��ƁE�E�E
|
�@�@�C�X���G���E�p���X�`�i�̌����ɗJ���̐��� |
|---|
�u�݂݂����v�����ǎ҂ł���C�����l�N�قǑO�Ƀp���X�`�i�̃A�g�t�@���i�W�w�Z�Ɍ��n�̒��\�W�̎w���ɎO�T�ԂقǕ��������Ƃ������m�ł��낤�B���{�̂m�o�n�@�l�u�p���X�`�i�q�ǂ��̃L�����y�[���v�����{�̉����Őݗ��C�^�c���Ă���W�w�Z�ł���B���C�p���X�`�i�̎q�ǂ��B����ɂ��炳��C�O�S�l����q�ǂ��B�̖����D���C�����̕ۏႪ�Ȃ������𑗂��Ă���B���m�F���ł͂��邪�C�p���X�`�i�̘W�����C�X���G�����̍U���ŏe�e���C���S�����Ƃ������Ă���B
���C�����C�G���T�����̃C�X�������̐��n�C���_�����̒Q���̕ǁC�L���X�g���̐����拳���n�i�U����K�˂��B�Ɠ����ɂ��ꂼ��̐��n�D�Ґ푈�̒������j�̒��Ő�����Ȃ��l�̎������邱�Ƃ������ɒm�邱�Ƃ��ł����B���͈ȑO���疳�@�������C�G���T�����̒n��K�ˁC�@���ɑ���^��͈�w���܂����B���n�Ȃǂ��Ȃ��K�v�Ƃ���̂��B�M����C�����C���n�͐S�ɂ���Ηǂ��C�y�n��ꏊ�ɂ�����邱�Ǝ��̂��u�F�v�ł���C�u��v�𗝉����Ă��Ȃ��ƁI�B
�@���������炷�l���~���\���̕�����]�������Ƃ��Ă��C�C�X���G���E�p���X�`�i�̗͂̑����͖ڂ�w�������Ȃ錻���ł���B���C�������Đ����Ă��Ȃ���C�����n���̏�ŁC�����l�Ԃɑ��ċ@�֏e�������u�E���v�s�ׂ𐳓�������_�������藧���Ƃ��C���̂��̎���ɓ������s�ł��邱�Ƃ��M�����Ȃ��B���{�͐�������ő����̕��a�Ȃǖ��S�ʼnᒠ�̊O�����C���ꂾ�������̍�������Ȃ��琭���ł��C�����āC�{���͐l���~���ׂ��@���ł��}���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B����Ȍ����������Ă������̂��낤���B
�U��Ԃ�C���{���푈�ɑ����������C���{�ł������̏�Q�҂��u�����̖��ɗ����Ȃ��ҁv�Ƃ��Ă������������C�Љ�I����D����Ă����B��Q�҂͂��������̘͂_���̒��ŁC�\�͂Ɏア����ɂ���B�푈�Ƃ����X�������̒��ŁC�l�������W(���イ���)����C�l�̑����Ɩ��͌y������C���ɓG���l���E�l���邱�Ƃ����������p�Y�̂悤�Ɍ����B���̒��ŁC�ǂꂾ����Q���������l�������Љ�I�ɕs�K�v���Ƃ����_���ŎE����Ă������C����́w�i�`�X�h�C�c�Ə�Q�ҁu���y���v�v��x�i���㏑�فj�̒��ł��Љ�ꂽ�C�܂��Ɏ����Ȃ̂ł���B
��Q���҂ɁC�����ċ���Ɍg����Ă��鎄�����́C�܂��͐푈�ɂȂ�悤�Ȏ��Ԃ��Ȃ�Ƃ��Ă��h���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂��B��Q�҂��Љ�I��҂Ƃ�����킯�ł͂Ȃ����C�Љ�I��҂Ɋ֗^����҂����炱���C�u���҂̘_���v�ɒ�R�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��C���҂̘_���̌��ʂƂ��Ă̐푈�ɂ����ƊS�ƁC����ɐ��~�Ɨ}�~�̈ӌ��𑗂�˂Ȃ�Ȃ��ƍl���Ă���B
���n�D�҂̂��߂̎E�l��e�F����@���Ȃ�C���݂̉��l�͂Ȃ��B���Ȃ�E�l�ȂǑ��݂��Ȃ��Ǝv�����C�Ƃɂ����l���l���E���������Ƃ𐳓����ł���_���͑��݂��Ȃ��B���ɐ킢�ɂȂ����Ƃ���Ȃ�C�͂�������������������ׂ��Ȃ̂��B
�Ȃɂ͂Ƃ�����C�C�X���G�����{�ɂ͎��d�ƖҏȂ𑣂������B
���l��
�P�Q�����{����̒�������Q����N��������J��Ԃ��Ă���܂����B
���s���啝�ɒx��܂������Ƃ����l�ѐ\���グ�܂��B
�y�ڎ��z
���y�[�p�[���f�B�A�ɂ��u�݂݂����v�w�ǂ̂��U����
�@�u�݂݂����v�͌��ɂQ��̒���o�ŕ��ł��B����̂́u�݂݂����v���w�NJ�]�̕��́A��L�̂�������e-mail�ł����O�A���Z�����������������B�܂�Ԃ��A���{���ƍw�Ǘ��U���p���������肢�����܂��B�w�Ǘ��́A���R�O�O�~�ł��B
�N�x���߂ŁA�e�N�x�Ƃ��A�R���܂ł̎c�����~�R�O�O�~��O�[���Ă��������܂�
�B�Ȃ��A���쌠�̊W�ŁA�z�[���y�[�W�ʼn{���ł���L���́A����̂́u�݂݂����v�̂����A�C���^�[�l�b�g�ł̌��J������ꂽ�L�����e�Ɍ���܂��B
�y�ڎ��z | NEXT | BACK |�u�݂݂����v�z�[���y�[�W
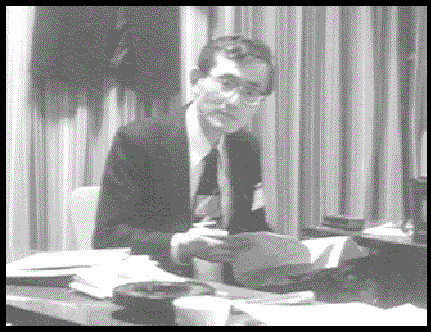
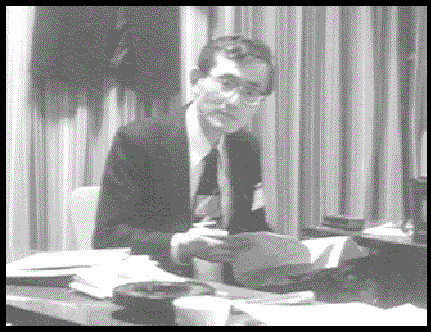 �P�P���P�W�������搶�����S���Ȃ�ɂȂ�ꂽ�B���s�ł̕⒮�����̍ۂɁC�������̕a�@�ɂ��������Ɏf�킳���Ă����������̂����C���̎��͓��a�����Ƃ͌����C�����̂悤�ɔw���s���ƐL���C�u����`�C�����������搶���������ǂ˂��C���ǁC�ނ��킩���ĂȂ��˂��v�Ƃ����悤�Ɍ���������]������Ă���ꂽ���Ƃ��v���o���B�x�b�h���ɏ������b�c�v���[�����u���Ă������悤�ɋL�������邪�C����������ŁC�^���m�C���炢�Ȃ班���͂킩�鎄�ł����߂ĕ����悤�ȃX�s�[�J�ł������ɂȂ肽���̂ł͂Ȃ����낤���Ǝv���Ȃ��璷�����w�Ɍ������ċA�����B������́C���s�W�w�Z���炲����܂ŁC�_�˘W�w�Z�̓����̒��\��C�����������搶�Ǝ��̎Ԃł����肵�����Ƃ�����B�a�ł����Ԃ�Ƃ�����܂Ŏ��Ԃ��������Ă��܂������C�Ԓ��C�搶�̂�����̃��X�j���O���[���̘b���f���Ă����̂ŁC���͂Ă�����u�܁C������Ɗ���Ă����āE�E�E�v�Ƃ����|��������������̂Ǝv���Ă������C���̍ۂ͊ՐÂȍ���̂�����O����q�����������ɏI����Ă��܂����B�����P�R�N�قǑO�̂��Ƃł͂Ȃ����낤���E�E�E�B���̕⒮��t�B�b�e�B���O�̎t��������ƌ�����Ȃ�C��P�͌̈���G�搶�ł��낤�B����搶�ɂ͂��̑����Ƃ��w�ŃN���N���b�ƃg���}���Ȃ���C���Ƃ́u�ǂ���������悤�ɂȂ閂�p�v�Ńt�B�b�e�B���O�����Ă����悤�ȋC�����Ă����B���͂���͔��ɑ厖�Ȃ��ƂŁC�u���\������̂͂Ȃ���̂��C����͐l�Ԃ̐S�̖��ł���v�Ƃ̋��������B����C�����Q�Q�̎��́C�����Ɂu�Z�p�v������Ȃ����Ƃ������Ă������C�����@�̑Ό��Ɗ����̒��ŁC���_�̂悤�Ȃ��̂�~�������Ă����B���̐܂�C���É��Œ��o�����Q������J�Â���C�Q�������܂�C�����搶�̔��\��q�����邱�Ƃ��ł����B�r�o�k�O������p���āC�����ƃC�R���C�Y�ő��p臒l��]�����C�܂��C����臒l�ƒP�ꗹ��x�Ƃ̊W���N���A�Ɏ����ꂽ�����\�ł͂Ȃ��������Ǝv���B���͂��̌�����̋x�ݎ��ԂɁC���[�v�̍��M�̂��Ƃ����₳���Ă����������̂����C���ɃX���X���b�Ɛ}�ʂ������C�u�����ăL�~�˂��C����͂����Ȃ����C�R���͓̂�����O����Ȃ��́B������ɂˁE�E�E�v�ƁC���[�v�ɗ���Ȃ����s�����̒����������Ԃ�ƕ������Ă����������B���̌�C���x�����s�{���W�w�Z�̒������ɗ�����点�Ă����������ƂɂȂ����B�ǖʂɎq�ǂ��̖��O�ƕ⒮��̊�킪���R�ƌf������C�l�t�@�C�����P���P���Ă��˂��ɒԂ����Ă���l�q��q�������B�a���j�̃^�}�S�Ɍ������C�_�C���������Ĕ����Ȓ��������邨�p��q�������B���̐��R���͓����̓����W�ɂ͂Ȃ����̂ł������B�������̌l�t�@�C�����̂������Ă��������Ȃ���C�u�������������P�[�X�ɂ́C���������Ώ����E�E�E�v�ƂP�P����������ē����ɋA��C���ۂɎ����Ă݂��B�V�[�����X��284PPAGCI�C���Ẳ��҃I�[�e�B�R����E28P�C���C�f�b�N�X��A12T��A18T�i����͎K�т邯�NJm���ɉ����̂����⒮�킾�����j���������B�������狞�s�W�̒������̋@��ɂ͋����Ă����B�J�Z�b�g�e�[�v���R�[�_�̓i�J�~�`�C�X�s�[�J�͂i�a�k�̃V���O���R�[���E�E�E�C�I�[�f�B�I������Ă���l�Ԃł���ΐ����̋@�����ł���B�u�������v��ڎw���p���C�P���a�C�Q���a�������ɂ������v�Z���C�u�����ʂɂ�����C����Ȃɑ傫���̂ɁC���ꂪ�����ł�����Č����̂��v�Ƃ����悤�Ȏp���Ɏ��͉��ɂ������搶�́C�܂��ɔw���L�т��������������C�傢�Ɋw�����Ă����������B���s�W�w�Z���ސE��C�V���w����n���S�łP�w�s�����ꏊ�Ƀ}���V�����̈ꎺ������u�V���q�������O�N���j�b�N�v���J�݂��ꂽ�B���s�W�w�Z���ォ��\���L�܂�C�F�{���n�ߋ�B�C���l�����甩���搶�̂��Ƃɕ⒮��̃t�B�b�e�B���O���k�ɖK���e�q���₦���C�ɒO��`�߂��ɏꏊ���m�ۂ��ꂽ�Ǝf�����B�����ɂ����x�����ז������Ă����������B���ւ�����ĉE�艜�ɏ����ȑ䏊������C�①�ɂ��������B���ɂ͂k�g�P�S���u���Ă������B���I���̃E�H�[�u���g�[�����M��ƁC�V�[�����X�̌^�Ԃ͖Y�ꂽ���C�C���s�[�_���X�ƕ⒮��̉����������Ƃ������ȑg�ݍ��킹�̑���킪�������B�ǂɂ͓����C�����{�̕⒮��t�B�b�e�B���O�̑��l�� �n�ӎ��Y�搶�̃N���j�b�N���܂˂��āC�S���̂ǂ����牽�l���Ă��邩���킩��悤�ɁC���{�̒n�}�ɂP�O�l�̐j�C�P�l�̐j�ƐF�����߂��j���h�����Ă����B�����̂��łɑ��ɍs�����Ƃ��ł���`�����X������ƁC�搶�̃N���j�b�N�������˂��B���̓����F�{����e�q�����Ă����B���k���́E�E�E�m���C�P���ԂR�O�O�O�~�������悤�ȋC������B�ł��C���w���Ă��鎄���������т�Ă��܂��قǁC���̕ی�҂̕��̘b���C���k���Ă����B�⒮��̃t�B�b�e�B���O�͂����Ƃ����ɏI����Ă���̂ł��邪�C���X�Ƌ����i�w�̑��k���Ă���ꂽ�B�����搶�́C�������E�������ł��苳��҂ł������B�a���j�ɗ����������Ȃ���C���̑����̌���������(��)�Ă���ꂽ�̂��B�R���ԋ߂��ɂȂ������낤���C����ł��u�R�O�O�O�~�v�Ȃ��C�悤�₭�e�q���A��ƁC�①�ɂ���ʃr�[���������Ă����C�u�܂��C���݂܂��傤��v�Ƃ��̂܂ܐ��{�̃r�[���������낤���B������v���C���̎����炢���炲�̒����悭�Ȃ������̂��C�u���̍��˂��E�E�E�v�Ɖ��x�����f������x�Ɋʃr�[���̖{��������C�߂��̂�������[���ł̂��H���������Ă����悤�ȋC������B���p�����肨�ʖ�ɂ������V�ɂ��Q�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�ł������炭�C�����̊W�҂Ɉ͂܂ꂽ�����ł��������낤�B�����搶�́C�����{�̒��\�̐��ł���C���C���C�ȋߋE����I�[�f�B�I���W�[�̊J�c�̈�l�ł�����B�搶�̓p�[�t�F�N�g��ڎw���搶�ł������B�������̌��e��e�L�X�g�����߂Ă��Ȃ���C���Ȃɐ��Ȃ��d�˂��邽�߂ɁC���ɏo�����͔̂��ɏ��Ȃ��B���̌������ƙ{���ʂ��́C�������Ƃ��Ă̐搶�̐��i�䂦�ł��낤�B����䂦�Ɏf���Ƃ���C����N�܂Łu���o��Q������ɂ����鉹�������̊�b�v����e�L�X�g��Z�߂��Ă������o�łɂ͎����Ă��Ȃ��ƕ������B�����搶���S���Ȃ����B�搶�ɂ��܂Ƃ߂��������������Ƃ͂���Ȃɂ���B�܂��܂��茳�ɃS���S�����Ă���B�ł��C�S���Ȃ��Ă��܂�ꂽ�B�{���ɖ{���Ɏ��c���ꂽ�Ƃ����悤�ȋC�����ɂ����Ȃ�B���n�ɂāC�����V�̎��Ԃ��}���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��������C�u�����搶�̈̋Ƃ��㐢�Ɉ��p���C����I�[�f�B�I���W�[�̗���������ɂ���ɐ}��g������X�͑����ꂽ�̂��v�Ɗ����C�勃�����Ă��܂����B�u�搶�C���肪�Ƃ��������܂����B�킩��Ȃ����ƈ�t�����ǁC���C�Ȃ�Ƃ�����Ă܂��B�v
�P�P���P�W�������搶�����S���Ȃ�ɂȂ�ꂽ�B���s�ł̕⒮�����̍ۂɁC�������̕a�@�ɂ��������Ɏf�킳���Ă����������̂����C���̎��͓��a�����Ƃ͌����C�����̂悤�ɔw���s���ƐL���C�u����`�C�����������搶���������ǂ˂��C���ǁC�ނ��킩���ĂȂ��˂��v�Ƃ����悤�Ɍ���������]������Ă���ꂽ���Ƃ��v���o���B�x�b�h���ɏ������b�c�v���[�����u���Ă������悤�ɋL�������邪�C����������ŁC�^���m�C���炢�Ȃ班���͂킩�鎄�ł����߂ĕ����悤�ȃX�s�[�J�ł������ɂȂ肽���̂ł͂Ȃ����낤���Ǝv���Ȃ��璷�����w�Ɍ������ċA�����B������́C���s�W�w�Z���炲����܂ŁC�_�˘W�w�Z�̓����̒��\��C�����������搶�Ǝ��̎Ԃł����肵�����Ƃ�����B�a�ł����Ԃ�Ƃ�����܂Ŏ��Ԃ��������Ă��܂������C�Ԓ��C�搶�̂�����̃��X�j���O���[���̘b���f���Ă����̂ŁC���͂Ă�����u�܁C������Ɗ���Ă����āE�E�E�v�Ƃ����|��������������̂Ǝv���Ă������C���̍ۂ͊ՐÂȍ���̂�����O����q�����������ɏI����Ă��܂����B�����P�R�N�قǑO�̂��Ƃł͂Ȃ����낤���E�E�E�B���̕⒮��t�B�b�e�B���O�̎t��������ƌ�����Ȃ�C��P�͌̈���G�搶�ł��낤�B����搶�ɂ͂��̑����Ƃ��w�ŃN���N���b�ƃg���}���Ȃ���C���Ƃ́u�ǂ���������悤�ɂȂ閂�p�v�Ńt�B�b�e�B���O�����Ă����悤�ȋC�����Ă����B���͂���͔��ɑ厖�Ȃ��ƂŁC�u���\������̂͂Ȃ���̂��C����͐l�Ԃ̐S�̖��ł���v�Ƃ̋��������B����C�����Q�Q�̎��́C�����Ɂu�Z�p�v������Ȃ����Ƃ������Ă������C�����@�̑Ό��Ɗ����̒��ŁC���_�̂悤�Ȃ��̂�~�������Ă����B���̐܂�C���É��Œ��o�����Q������J�Â���C�Q�������܂�C�����搶�̔��\��q�����邱�Ƃ��ł����B�r�o�k�O������p���āC�����ƃC�R���C�Y�ő��p臒l��]�����C�܂��C����臒l�ƒP�ꗹ��x�Ƃ̊W���N���A�Ɏ����ꂽ�����\�ł͂Ȃ��������Ǝv���B���͂��̌�����̋x�ݎ��ԂɁC���[�v�̍��M�̂��Ƃ����₳���Ă����������̂����C���ɃX���X���b�Ɛ}�ʂ������C�u�����ăL�~�˂��C����͂����Ȃ����C�R���͓̂�����O����Ȃ��́B������ɂˁE�E�E�v�ƁC���[�v�ɗ���Ȃ����s�����̒����������Ԃ�ƕ������Ă����������B���̌�C���x�����s�{���W�w�Z�̒������ɗ�����点�Ă����������ƂɂȂ����B�ǖʂɎq�ǂ��̖��O�ƕ⒮��̊�킪���R�ƌf������C�l�t�@�C�����P���P���Ă��˂��ɒԂ����Ă���l�q��q�������B�a���j�̃^�}�S�Ɍ������C�_�C���������Ĕ����Ȓ��������邨�p��q�������B���̐��R���͓����̓����W�ɂ͂Ȃ����̂ł������B�������̌l�t�@�C�����̂������Ă��������Ȃ���C�u�������������P�[�X�ɂ́C���������Ώ����E�E�E�v�ƂP�P����������ē����ɋA��C���ۂɎ����Ă݂��B�V�[�����X��284PPAGCI�C���Ẳ��҃I�[�e�B�R����E28P�C���C�f�b�N�X��A12T��A18T�i����͎K�т邯�NJm���ɉ����̂����⒮�킾�����j���������B�������狞�s�W�̒������̋@��ɂ͋����Ă����B�J�Z�b�g�e�[�v���R�[�_�̓i�J�~�`�C�X�s�[�J�͂i�a�k�̃V���O���R�[���E�E�E�C�I�[�f�B�I������Ă���l�Ԃł���ΐ����̋@�����ł���B�u�������v��ڎw���p���C�P���a�C�Q���a�������ɂ������v�Z���C�u�����ʂɂ�����C����Ȃɑ傫���̂ɁC���ꂪ�����ł�����Č����̂��v�Ƃ����悤�Ȏp���Ɏ��͉��ɂ������搶�́C�܂��ɔw���L�т��������������C�傢�Ɋw�����Ă����������B���s�W�w�Z���ސE��C�V���w����n���S�łP�w�s�����ꏊ�Ƀ}���V�����̈ꎺ������u�V���q�������O�N���j�b�N�v���J�݂��ꂽ�B���s�W�w�Z���ォ��\���L�܂�C�F�{���n�ߋ�B�C���l�����甩���搶�̂��Ƃɕ⒮��̃t�B�b�e�B���O���k�ɖK���e�q���₦���C�ɒO��`�߂��ɏꏊ���m�ۂ��ꂽ�Ǝf�����B�����ɂ����x�����ז������Ă����������B���ւ�����ĉE�艜�ɏ����ȑ䏊������C�①�ɂ��������B���ɂ͂k�g�P�S���u���Ă������B���I���̃E�H�[�u���g�[�����M��ƁC�V�[�����X�̌^�Ԃ͖Y�ꂽ���C�C���s�[�_���X�ƕ⒮��̉����������Ƃ������ȑg�ݍ��킹�̑���킪�������B�ǂɂ͓����C�����{�̕⒮��t�B�b�e�B���O�̑��l�� �n�ӎ��Y�搶�̃N���j�b�N���܂˂��āC�S���̂ǂ����牽�l���Ă��邩���킩��悤�ɁC���{�̒n�}�ɂP�O�l�̐j�C�P�l�̐j�ƐF�����߂��j���h�����Ă����B�����̂��łɑ��ɍs�����Ƃ��ł���`�����X������ƁC�搶�̃N���j�b�N�������˂��B���̓����F�{����e�q�����Ă����B���k���́E�E�E�m���C�P���ԂR�O�O�O�~�������悤�ȋC������B�ł��C���w���Ă��鎄���������т�Ă��܂��قǁC���̕ی�҂̕��̘b���C���k���Ă����B�⒮��̃t�B�b�e�B���O�͂����Ƃ����ɏI����Ă���̂ł��邪�C���X�Ƌ����i�w�̑��k���Ă���ꂽ�B�����搶�́C�������E�������ł��苳��҂ł������B�a���j�ɗ����������Ȃ���C���̑����̌���������(��)�Ă���ꂽ�̂��B�R���ԋ߂��ɂȂ������낤���C����ł��u�R�O�O�O�~�v�Ȃ��C�悤�₭�e�q���A��ƁC�①�ɂ���ʃr�[���������Ă����C�u�܂��C���݂܂��傤��v�Ƃ��̂܂ܐ��{�̃r�[���������낤���B������v���C���̎����炢���炲�̒����悭�Ȃ������̂��C�u���̍��˂��E�E�E�v�Ɖ��x�����f������x�Ɋʃr�[���̖{��������C�߂��̂�������[���ł̂��H���������Ă����悤�ȋC������B���p�����肨�ʖ�ɂ������V�ɂ��Q�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�ł������炭�C�����̊W�҂Ɉ͂܂ꂽ�����ł��������낤�B�����搶�́C�����{�̒��\�̐��ł���C���C���C�ȋߋE����I�[�f�B�I���W�[�̊J�c�̈�l�ł�����B�搶�̓p�[�t�F�N�g��ڎw���搶�ł������B�������̌��e��e�L�X�g�����߂Ă��Ȃ���C���Ȃɐ��Ȃ��d�˂��邽�߂ɁC���ɏo�����͔̂��ɏ��Ȃ��B���̌������ƙ{���ʂ��́C�������Ƃ��Ă̐搶�̐��i�䂦�ł��낤�B����䂦�Ɏf���Ƃ���C����N�܂Łu���o��Q������ɂ����鉹�������̊�b�v����e�L�X�g��Z�߂��Ă������o�łɂ͎����Ă��Ȃ��ƕ������B�����搶���S���Ȃ����B�搶�ɂ��܂Ƃ߂��������������Ƃ͂���Ȃɂ���B�܂��܂��茳�ɃS���S�����Ă���B�ł��C�S���Ȃ��Ă��܂�ꂽ�B�{���ɖ{���Ɏ��c���ꂽ�Ƃ����悤�ȋC�����ɂ����Ȃ�B���n�ɂāC�����V�̎��Ԃ��}���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��������C�u�����搶�̈̋Ƃ��㐢�Ɉ��p���C����I�[�f�B�I���W�[�̗���������ɂ���ɐ}��g������X�͑����ꂽ�̂��v�Ɗ����C�勃�����Ă��܂����B�u�搶�C���肪�Ƃ��������܂����B�킩��Ȃ����ƈ�t�����ǁC���C�Ȃ�Ƃ�����Ă܂��B�v
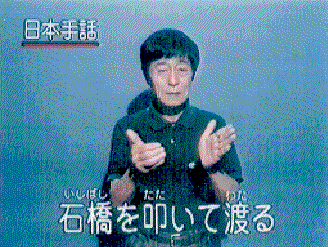 �u���̃r�f�I�́E�E�E�v�i������̈ē����j�{�҂́A����悭�g���邱�Ƃ̑�����\�I�ȁu���Ƃ킴�v�V�O���I�сA���^���Ă��܂��B�܂����{��b�Łu���Ƃ킴�v���̂������A���ɂ��́u���Ƃ킴�v�̈Ӗ���p�����{��b�ʼn�����Ă��܂��B�܂��A�t�^�̉�����ɂ́A���^�����u���Ƃ킴�v�Ƃ��̉���̓��{����Ă��܂��B�悸�A�����Ŏ�b���l���Ă��������A���̌�r�f�I�����āA�m�F������A�ӏ܂�����A�͕킵���肷����@������܂��B�Â�����`�����A�����̐l�X�Ɏg���Ă�����������́u���Ƃ킴�v�̒�����ɓ����Y�搶���I�����A����ɐ搶�̓Ƒn�����������Ă킩��Ղ����������ꂽ�\���ɂ��Ă��܂��B�w�Z��c�́A�T�[�N���̊F�l�̊ԂŁA���̃r�f�I�����������Ɏ�b�\���̗ւ��L���āA�V���Ȉӌ��₲��Ă������ǂɂ����������B
�u���̃r�f�I�́E�E�E�v�i������̈ē����j�{�҂́A����悭�g���邱�Ƃ̑�����\�I�ȁu���Ƃ킴�v�V�O���I�сA���^���Ă��܂��B�܂����{��b�Łu���Ƃ킴�v���̂������A���ɂ��́u���Ƃ킴�v�̈Ӗ���p�����{��b�ʼn�����Ă��܂��B�܂��A�t�^�̉�����ɂ́A���^�����u���Ƃ킴�v�Ƃ��̉���̓��{����Ă��܂��B�悸�A�����Ŏ�b���l���Ă��������A���̌�r�f�I�����āA�m�F������A�ӏ܂�����A�͕킵���肷����@������܂��B�Â�����`�����A�����̐l�X�Ɏg���Ă�����������́u���Ƃ킴�v�̒�����ɓ����Y�搶���I�����A����ɐ搶�̓Ƒn�����������Ă킩��Ղ����������ꂽ�\���ɂ��Ă��܂��B�w�Z��c�́A�T�[�N���̊F�l�̊ԂŁA���̃r�f�I�����������Ɏ�b�\���̗ւ��L���āA�V���Ȉӌ��₲��Ă������ǂɂ����������B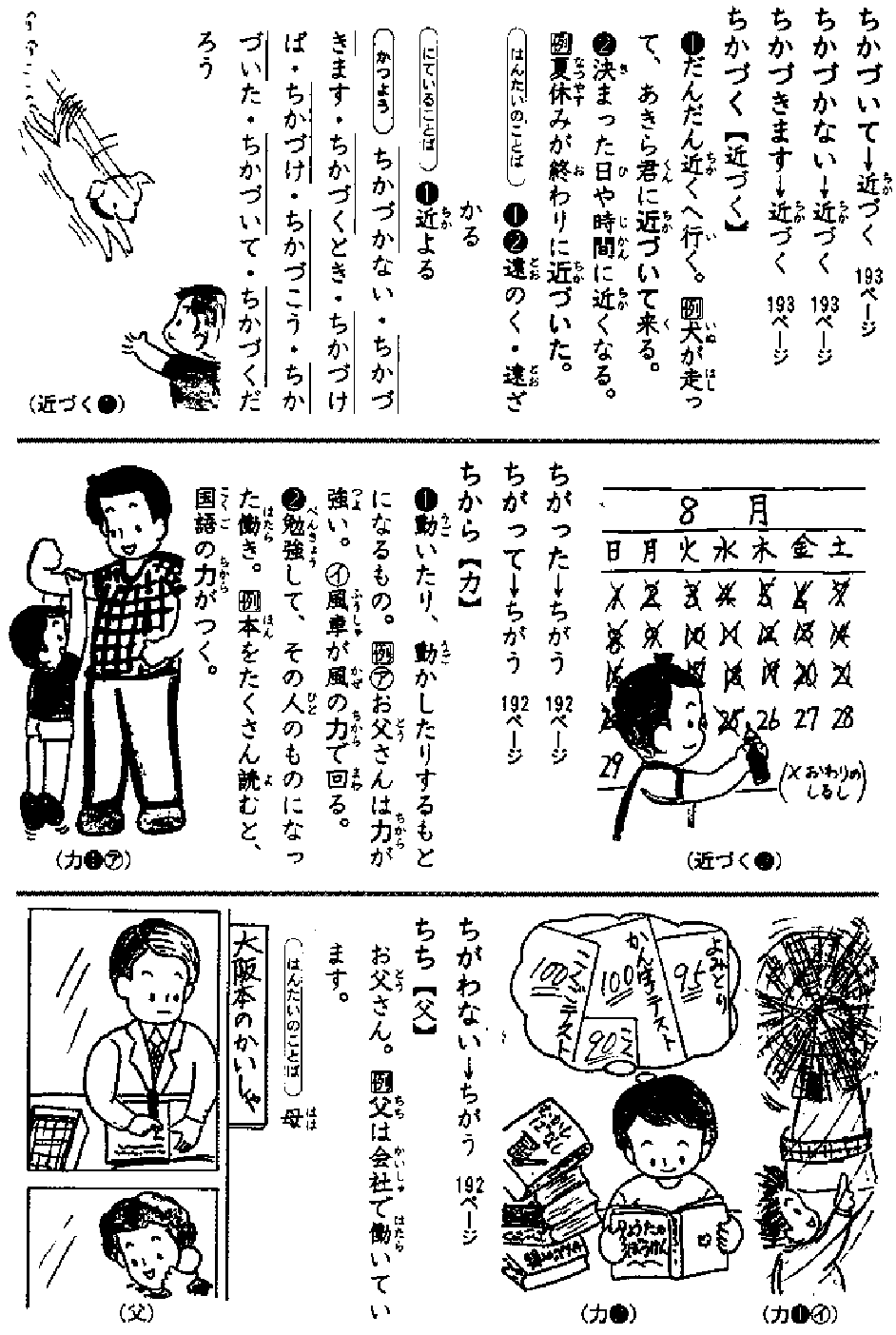 �������E�̍ۂ͂��Ԃ�p�쏑�X����o�ł���Ă����u���ƂΊG���Ă�v�𗘗p���Ă����悤�ȋL��������B������Ƃ������Ƃ�`���������ɓK�ȊG�Ǝg�p�@���q�ǂ����g�����ׂ��鎫�T�͂Ȃ��Ȃ��Ȃ��B���́u�������G���Ă�v�́C���������Y�݂̌��ʂȂ̂��낤���C�����s���W�w�Z�̐搶�R�l�����N�̘W�w�Z�ł̋�����H�����ƂɕҏW�ɂ����������Ă�ł���B���ꂾ���Ɋ��p�`�Œ��ׂ�ꂽ��C�C���X�g��ᕶ�ɂ킩��₷�����̂��I��Ă���B�����ɂ��W�w�Z�I�ȏ�ʐݒ�Ɋ�Â��ᕶ�������C�ǂ݂Ȃ���u��������������ʂ��������Ȃ��v�ƃj���j�����Ă��܂����B�C���X�g���L�x�Ȃ̂ŁC�C���X�g�����Ȃ���G�{�̂悤�Ɍ��Ă������Ƃ��ł��C�c�t���S���炢���珬�w���܂Ŏg���邩�Ȃ��Ǝv���B�P�� �Q�O�O�O�~�i�ŁE�������݁j�Ȃ��C�ʏ�̏��X�ł͍w���ł��Ȃ��̂ŁC���L�̕��@�ł��������B
�������E�̍ۂ͂��Ԃ�p�쏑�X����o�ł���Ă����u���ƂΊG���Ă�v�𗘗p���Ă����悤�ȋL��������B������Ƃ������Ƃ�`���������ɓK�ȊG�Ǝg�p�@���q�ǂ����g�����ׂ��鎫�T�͂Ȃ��Ȃ��Ȃ��B���́u�������G���Ă�v�́C���������Y�݂̌��ʂȂ̂��낤���C�����s���W�w�Z�̐搶�R�l�����N�̘W�w�Z�ł̋�����H�����ƂɕҏW�ɂ����������Ă�ł���B���ꂾ���Ɋ��p�`�Œ��ׂ�ꂽ��C�C���X�g��ᕶ�ɂ킩��₷�����̂��I��Ă���B�����ɂ��W�w�Z�I�ȏ�ʐݒ�Ɋ�Â��ᕶ�������C�ǂ݂Ȃ���u��������������ʂ��������Ȃ��v�ƃj���j�����Ă��܂����B�C���X�g���L�x�Ȃ̂ŁC�C���X�g�����Ȃ���G�{�̂悤�Ɍ��Ă������Ƃ��ł��C�c�t���S���炢���珬�w���܂Ŏg���邩�Ȃ��Ǝv���B�P�� �Q�O�O�O�~�i�ŁE�������݁j�Ȃ��C�ʏ�̏��X�ł͍w���ł��Ȃ��̂ŁC���L�̕��@�ł��������B �{���͘W�w�Z���@�C��w���S�C������Ă���ꂽ�c�����q�搶�̎���o�ŁB���ꂾ���ɁC���o��Q�����f�f���C�W�w�Z���ł̋���⏬�w�Z�����ɂ��āC��������ʂ���ł��낤��ʂ�ʂ��ė��������i�����悤�ȍ\���Ɠ��e�ɂȂ��Ă���B
�{���͘W�w�Z���@�C��w���S�C������Ă���ꂽ�c�����q�搶�̎���o�ŁB���ꂾ���ɁC���o��Q�����f�f���C�W�w�Z���ł̋���⏬�w�Z�����ɂ��āC��������ʂ���ł��낤��ʂ�ʂ��ė��������i�����悤�ȍ\���Ɠ��e�ɂȂ��Ă���B ���w���厖�̗щ��}�搶�́C�{���́u�͂��߂Ɂv�Ŗ{���̕K�v����W�X�Ɛ����Ă���B�u��X���o��Q���̋���Ɍg���҂́C���k��l�ЂƂ�̎��Ă�͂��ő���L���Ă���ƌ������̂ł��낤���H�v�P�Q�O�N���钷�����o��Q������̗��j�̒��ŁC��b�@�Ɏn�܂�C���b�@�C�⒮�C�ēx�C��b���܂ރR�~���j�P�|�V�������[�h�̐��������}���C���͐����Ă����B�������C�u����w�ю���l����́v���\�ɐg�ɂ��邱�ƂɎ������ł��낤���B���̂�����ɒ��o��Q������̑傫�ȉۑ肪���邩�Ǝv���B���āC�{���͒}�g��w�����W�w�Z���w���̎��H�E�������ł���B���̒��ɂ͓��X�C�����I�w�K�Ɍ��������H���Ïk����Ă���B�ēx�C�ю厖�̕������p����B
���w���厖�̗щ��}�搶�́C�{���́u�͂��߂Ɂv�Ŗ{���̕K�v����W�X�Ɛ����Ă���B�u��X���o��Q���̋���Ɍg���҂́C���k��l�ЂƂ�̎��Ă�͂��ő���L���Ă���ƌ������̂ł��낤���H�v�P�Q�O�N���钷�����o��Q������̗��j�̒��ŁC��b�@�Ɏn�܂�C���b�@�C�⒮�C�ēx�C��b���܂ރR�~���j�P�|�V�������[�h�̐��������}���C���͐����Ă����B�������C�u����w�ю���l����́v���\�ɐg�ɂ��邱�ƂɎ������ł��낤���B���̂�����ɒ��o��Q������̑傫�ȉۑ肪���邩�Ǝv���B���āC�{���͒}�g��w�����W�w�Z���w���̎��H�E�������ł���B���̒��ɂ͓��X�C�����I�w�K�Ɍ��������H���Ïk����Ă���B�ēx�C�ю厖�̕������p����B ���̑��u�́u�ԊO����M��ƃA���v����������e���r�̃����R���v�Ƃ������\���ɂȂ��Ă���B�e���r�ɐڑ������ԊO�������킩��C�ԊO���ɏ���ăe���r�̉������o�āC�茳�ɂ����M��ɓ͂��B��M�푤�ɂ̓A���v����������Ă��āC�e���r�̉�����������ăX�s�[�J����C�܂��͐ڑ������C���z���Ȃǂ��特�Ƃ��ďo�͂����悤�ɂȂ��Ă���B���C�e�탁�[�J�[�̃e���r�ɂ��킹���郊���R���@�\�������Ă���B���̑��u�̎�M��ɂ͂R�̓��͕��@���p�ӂ���Ă���B���͍��܂Ŏs�̂���Ă������l�̋@��ł́C���̃e���r�̉�������镔�������܂��ł��Ă��Ȃ����߂ɉ����e���r������o���Ȃ����Ƃɖ�肪�������B�{��͎莝���̃e���r�ɂ���ē��͕��@���I���ł��C���̕ӂ̑���ɂ̓u�����h�Ȃ�ł͂Ɗ��S�����B�ԊO�����g�p���邽�߉������ɂ߂ėǂ��B��M�푤�̓����X�s�[�J���܂��܂��B����ɖ{��̊J���҂͓�҂Ƃ������Ƃ������āC�C���z���W���b�N�𗘗p���ăV���G�b�g�C���_�N�^��O�����͒[�q�Ȃǂ���ĕ⒮��Ńe���r�̉������Ƃ��ł���B��r�I�y����ł���Ζ{�킾���ŏ\���Ƀe���r�̉������Ƃ��ł��悤�B�܂��C�����g���q�ǂ����������r���O�̒��ŏd�Ă���̂����C�u���p�i�v�Ƃ��Ă��\�ɒʗp����B
���̑��u�́u�ԊO����M��ƃA���v����������e���r�̃����R���v�Ƃ������\���ɂȂ��Ă���B�e���r�ɐڑ������ԊO�������킩��C�ԊO���ɏ���ăe���r�̉������o�āC�茳�ɂ����M��ɓ͂��B��M�푤�ɂ̓A���v����������Ă��āC�e���r�̉�����������ăX�s�[�J����C�܂��͐ڑ������C���z���Ȃǂ��特�Ƃ��ďo�͂����悤�ɂȂ��Ă���B���C�e�탁�[�J�[�̃e���r�ɂ��킹���郊���R���@�\�������Ă���B���̑��u�̎�M��ɂ͂R�̓��͕��@���p�ӂ���Ă���B���͍��܂Ŏs�̂���Ă������l�̋@��ł́C���̃e���r�̉�������镔�������܂��ł��Ă��Ȃ����߂ɉ����e���r������o���Ȃ����Ƃɖ�肪�������B�{��͎莝���̃e���r�ɂ���ē��͕��@���I���ł��C���̕ӂ̑���ɂ̓u�����h�Ȃ�ł͂Ɗ��S�����B�ԊO�����g�p���邽�߉������ɂ߂ėǂ��B��M�푤�̓����X�s�[�J���܂��܂��B����ɖ{��̊J���҂͓�҂Ƃ������Ƃ������āC�C���z���W���b�N�𗘗p���ăV���G�b�g�C���_�N�^��O�����͒[�q�Ȃǂ���ĕ⒮��Ńe���r�̉������Ƃ��ł���B��r�I�y����ł���Ζ{�킾���ŏ\���Ƀe���r�̉������Ƃ��ł��悤�B�܂��C�����g���q�ǂ����������r���O�̒��ŏd�Ă���̂����C�u���p�i�v�Ƃ��Ă��\�ɒʗp����B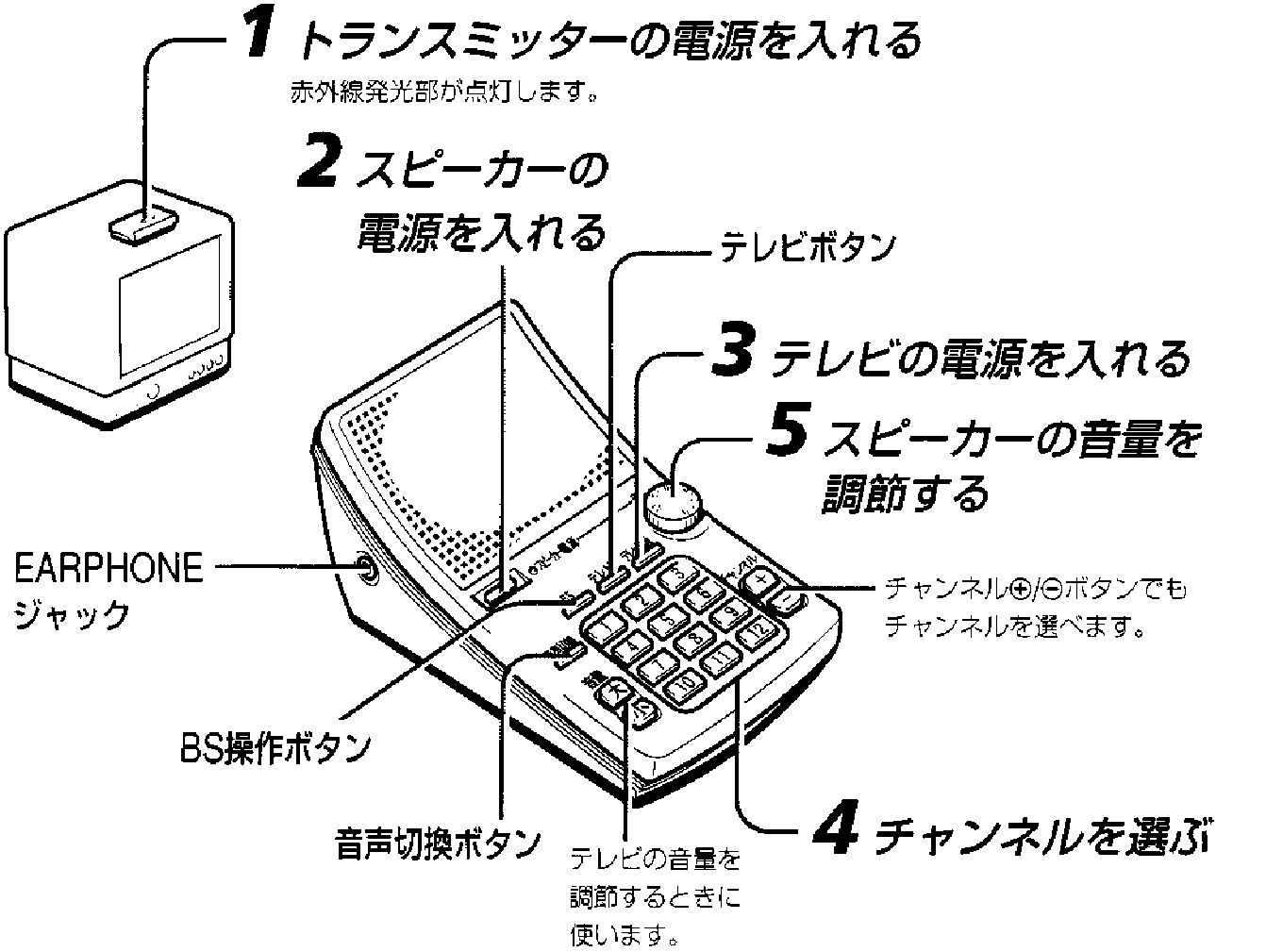 �Ȃ��C�ŋ߁C��M��ɂ`�b�A�_�v�^�ɂ��d���������ł��� �q�l�|�o�r�P�O�s�u�����C���i�b�v�ɉ�������B�V���i�ɂ͔��M�E��M�̑o���Ƃ��ĂQ��̂`�b�A�_�v�^�����Ă���ق��C�������傫���Ȃ�C���₷���Ȃ��Ă���B
�Ȃ��C�ŋ߁C��M��ɂ`�b�A�_�v�^�ɂ��d���������ł��� �q�l�|�o�r�P�O�s�u�����C���i�b�v�ɉ�������B�V���i�ɂ͔��M�E��M�̑o���Ƃ��ĂQ��̂`�b�A�_�v�^�����Ă���ق��C�������傫���Ȃ�C���₷���Ȃ��Ă���B